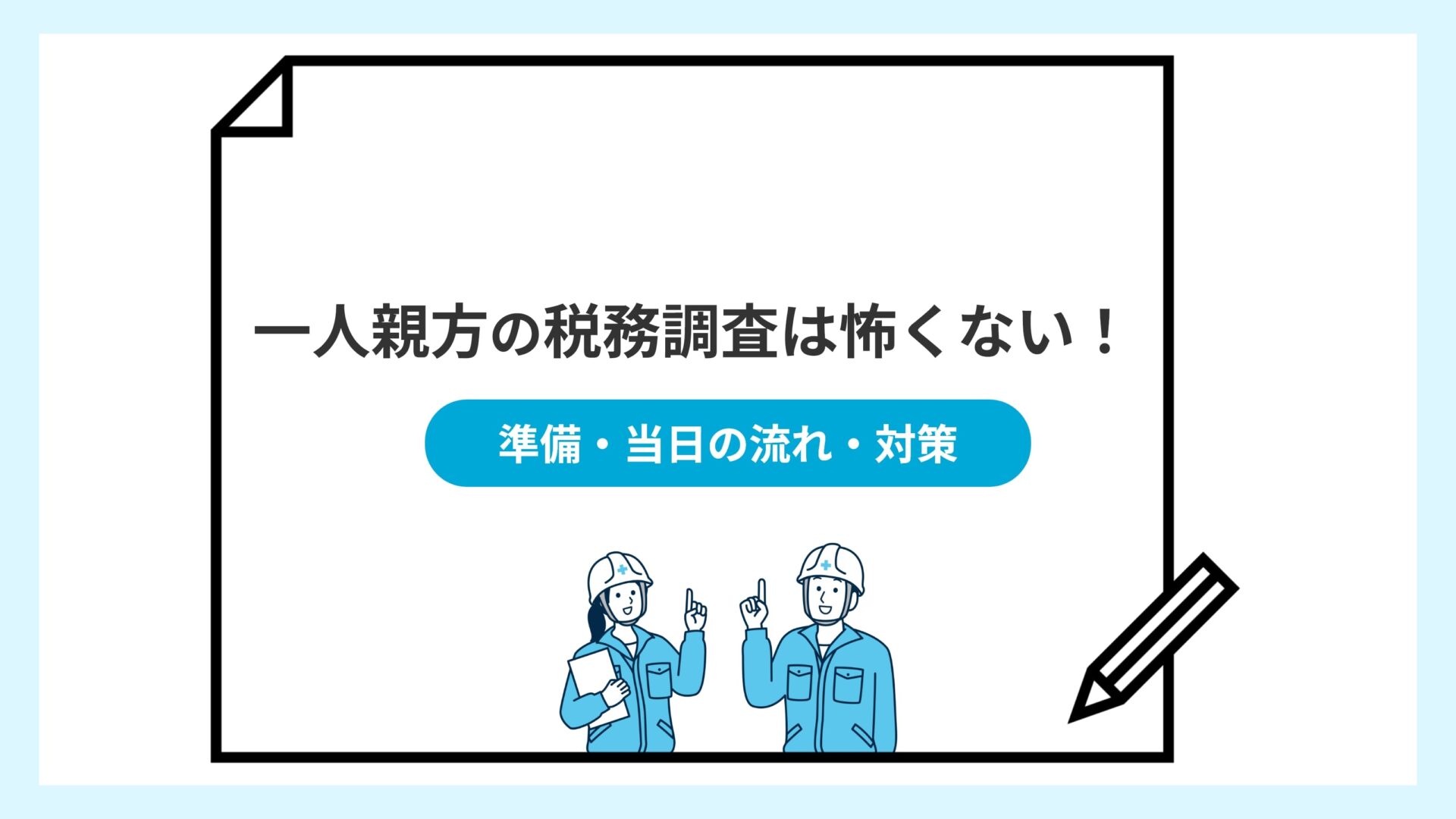税務調査の連絡が来たらどうしよう…
一人親方として事業を営む多くの方が、このような不安を抱えているのではないでしょうか?
テレビや雑誌で見る「ガサ入れ」のイメージが先行し、税務調査を必要以上に恐れてしまうのは当然のことです。
しかし、税務調査の多くは事前連絡のある「任意調査」であり、日頃から正しく申告と記帳を行っていれば、何も恐れることはありません。
この記事を読むことで、以下のことが理解できます。
- 税務調査の本当の目的と流れ
- どんな一人親方に調査が来やすいのか
- 今日からできる具体的な準備方法
- 調査当日の心構えと対応のコツ
- 税理士に依頼すべきタイミング
一人親方の税務調査とは?基本の「き」
税務調査は「脱税を疑われた人」だけに来るわけではなく、税務調査の本当の目的は「申告内容が正しいかどうかの確認」です。
多くの方が「税務調査=脱税の疑い」と誤解していますが、実際には、国税庁が適正な申告納税制度を維持するために行う行政調査の一環です。
税務署では以下の方法で調査対象を選定しています。
KSKシステム(国税総合管理システム)による抽出
全国の納税者の申告データを一元管理し、過去の申告内容や同業他社のデータと比較して、異常値や特異な変動が見られる事業者を自動的に抽出します。
資料情報の収集
取引先や金融機関などから収集した情報(資料情報)から、申告漏れの可能性が疑われる事業者が選定されます。
ランダム選定
上記に該当しなくても、一定の割合で無作為に選定されることもあります。
つまり、真面目に申告している一人親方でも調査の対象になる可能性はあります。
「調査が来た=何かやましいことがある」という考えは捨てましょう。
「白色申告」と「青色申告」で調査の確率は変わる?
結論から言うと、青色申告、特に65万円控除を受けている方が調査の確率は低くなる傾向にあります。
これは、青色申告(65万円控除)が複式簿記という正規の簿記原則に基づいた記帳を求めており、これが税務署からの信頼性の高さにつながるためです。
複式簿記による正確な記帳と証拠書類の保存は、それ自体が適切な申告の証明となるため、税務署も調査の優先順位を判断する一因としています。
| 申告の種類 | 求められる記帳 | 税務署からの信頼度 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 簡易な方法による記帳 | 普通 |
| 青色申告(10万円控除) | 簡易な方法による記帳 | やや高い |
| 青色申告(55/65万円控除) | 複式簿記による記帳 | 高い |
税務調査はいつ、どんな一人親方に来やすいのか?
国税庁の統計(令和4事務年度)によると、個人事業主に対する実地調査(税務署の職員が直接訪問して行う調査)の件数は年間約2万4千件です。
全国の申告所得税の納税者数が約670万人であることを考えると、実地調査を受ける年間の確率は約0.4%となります。
これは250年に1回程度の確率です。
ただし、これは全事業者を含めた平均値であり、後述する「調査対象に選ばれやすい特徴」に当てはまる場合は、確率はこれよりも高まります。
※実地調査以外に、電話や文書での問い合わせである「簡易な接触」は年間75万件以上あり、これらはより身近なものです。
調査のタイミングについて
申告から2~3年後が最も多いと言われています。
これは、税務署が申告書を受け取った後、KSKシステムでの分析や資料情報の収集・検討に時間を要するためです。
税務署が目を光らせる一人親方の5つの特徴
国税庁が公表する重点項目からも、調査対象となりやすい一人親方には明確な特徴があります。
売上が急増している(特に1,000万円を超えた事業者)
売上1,000万円は消費税の課税事業者となる基準です。
この境界線付近での売上操作(意図的に1,000万円未満に抑えるなど)が疑われやすくなります。
また、前年からの急激な売上増は、計上漏れがないかどうかの確認対象になりやすいです。
経費の割合が同業他社に比べて不自然に高い
KSKシステムは業種ごとの平均経費率を把握しています。
自身の経費率がその平均から大きく乖離している場合、架空経費やプライベート経費の計上がないか、重点的に見られる可能性があります。
現金商売がメインである
建設業の一人親方、個人向けの運送業、飲食業など、現金での取引が多い業種は、銀行振込などと比べて取引の記録が追いづらく、売上除外が起きやすいと見なされる傾向があります。
海外取引や新しい分野の取引がある
国税庁は、海外投資、暗号資産(仮想通貨)、インターネット取引(アフィリエイト、YouTubeなど)を重点的な調査対象として挙げています。
これらの取引は実態把握が難しいため、申告内容を詳細に確認されます。
過去に申告漏れや無申告の経歴がある
一度でも税務調査で重加算税などの重いペナルティを受けると、税務署のデータベースに記録され、その後も定期的な調査対象になりやすくなります。
税務調査では「何」を「何年分」見られるのか?調査項目の徹底解剖
調査期間は原則「3年分」、悪質な場合は「最大7年分」です。
調査の対象となる期間は、法律(国税通則法)で定められています。
- 通常の調査: 申告内容に大きな問題がなければ、過去3年分の申告が対象となります。
- 申告漏れなど: 調査の過程で申告漏れなどが発見された場合、5年分まで遡られることがあります。
- 偽装・隠蔽など悪質な場合: 意図的な所得隠しや証拠の改ざんなど、「偽りその他不正の行為」が認められた場合は、最大7年分まで遡って調査されます。
チェック項目一覧~売上からプライベート経費まで~
調査官が必ずチェックする項目を、実際の調査順序に沿って解説します。
売上関係
■売上計上漏れはないか?
- 請求書・契約書・納品書と、事業用口座の入金記録を照合し、金額や件数に漏れがないかを確認します。
- 年末年始の取引が、正しく年内に計上されているか(売上が発生した「年」をまたいでいないか)をチェックします。
■売上の計上時期は正しいか?
- 現主義の原則: 売上は、代金を受け取った日(入金日)ではなく、商品を引き渡した日やサービスを提供し終えた日に計上するのが原則です。特に工事の場合は、工事が完成した日(工事完成基準)が計上日となります。
経費関係
■架空経費、水増し経費はないか?
- 外注費: 支払先は実在するか、作業の実態はあるか、金額は適正か。家族への外注費は特に厳しく見られます。
- 交際費: 事業に関係のない家族や友人との飲食代が含まれていないか。
- 消耗品費: 大量の日用品など、事業との関連性が薄いものが含まれていないか。
■家事按分は妥当か?
- 自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費、通信費などを経費にするには、事業で使用した分を合理的な基準で分ける「家事按分」が必要です。
- 按分基準の例: 家賃(事業で使用する部屋の面積割合)、電気代(使用時間やコンセント数)、通信費(通話履歴や利用日数)、自動車関連費(走行距離の記録)。客観的に説明できる根拠資料が重要です。
その他の重要チェック項目
■在庫(棚卸資産)の計上は正しいか?
年末時点で残っている材料や商品を「棚卸資産」として正確に計上しているか。計上漏れは利益の過少申告に直結します。
■帳簿・書類の保存状況
法律で定められた期間、帳簿や書類が正しく保存されているかは、基本的ながら重要な確認項目です。
| 申告の種類 | 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|---|
| 青色申告 | ・仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿 ・貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類 ・領収書、預金通帳などの現金預金取引等関係書類 | 7年間 |
| 白色申告 | ・請求書、見積書、契約書などのその他の書類 ・収入金額や必要経費を記載した法定帳簿 ・任意で作成した帳簿や、請求書、領収書などの書類 | ・5年間 ・7年間 ・8年間 |
税務調査のための完璧な準備マニュアル【チェックリスト付】
税務調査対策の王道は「普段からきちんと記録し、証拠書類を整理しておく」ことです。
チェックリスト~今すぐ確認すべき9つのポイント~
- 帳簿(総勘定元帳など)は整備されているか?
- 売上に関する書類(請求書、契約書、納品書)は全て揃っているか?
- 経費に関する書類(領収書、レシート、クレジットカード明細)は全て揃っているか?
- 銀行の預金通帳(事業用・プライベート両方)は用意できているか?
- 棚卸表は作成されているか?(該当する場合)
- 家事按分の計算根拠を説明できる資料はあるか?
- 過去の確定申告書(3~5年分)の控えはあるか?
- 借入金の返済予定表はあるか?
- 国民健康保険・国民年金の支払証明書はあるか?
もし書類を紛失してしまった場合の対処法
領収書などを紛失しても、諦める必要はありません。
- 再発行の依頼
取引先に依頼して再発行してもらうのが最も確実です。「再発行」の印があっても税務上は有効です。
- 代替資料の活用
クレジットカードの利用明細書、銀行振込の控え、注文確認メールなども、取引の事実を証明する資料として認められる場合があります。
- 出金伝票の作成
どうしても証拠がない場合は、支払年月日、支払先、金額、内容を記載した「出金伝票」を自分で作成します。
ただし、これ単体では証拠能力が弱いため、他の資料と組み合わせることが望ましいです。
税務調査当日の流れと受け答えのシミュレーション
通常、調査の2〜3週間前に税務署の調査官から電話で事前通知があります。
この電話で、調査対象期間、希望日時、場所、準備すべき資料などが伝えられます。
仕事の都合など合理的な理由があれば、日程の調整は可能です。
調査当日(1〜2日間)の流れ
午前の部:事業概況のヒアリング(約2時間)
どのような事業を行っているか、家族構成、趣味など、雑談を交えながら事業の全体像について質問されます。
これは、申告された所得と生活レベルに不自然な点がないかなどを探る目的もあります。
午後の部:帳簿・書類の確認作業(約4時間)
調査官が持参した帳簿や書類を黙々と確認する時間です。
この間、不明点について個別に質問されることがあります。「この領収書は何の支払いですか?」といった具体的な質問が中心です。
受け答えの心得は「正直に」「簡潔に」「聞かれたことだけ」
調査官とのやり取りでは、余計なことを話して墓穴を掘らないことが重要です。
- 正直に答える: 嘘や曖昧な回答は、さらなる疑念を招きます。虚偽が発覚すれば重加算税の対象になりかねません。
- 簡潔に答える: 質問されたことに対して、まずは結論からシンプルに答えます。詳細な説明は、求められてからで十分です。
- 聞かれたことだけ答える: 関係のない情報まで自分から話す必要はありません。沈黙を恐れず、冷静に対応しましょう。
- 「確認します」も有効な回答: すぐに思い出せないことや、正確な情報が不明な場合は、無理に答えず「資料を確認して後ほど回答します」と伝えるのが賢明です。
調査後から納税まで:指摘事項があった場合の対処法
調査の結果、申告内容に誤りが見つかった場合は、「修正申告」を行い、不足していた税額とペナルティ(加算税・延滞税)を納付することになります。
修正申告と追徴課税の種類
- 修正申告書の提出: 調査官の指摘内容に納得した場合、自主的に申告内容を訂正する「修正申告書」を提出します。これを提出すると、原則としてその内容を覆すことはできません。
- 追徴課税の種類と税率: 本来納めるべきだった税額に加え、以下のペナルティが課される場合があります。
| 加算税の種類 | 適用されるケース | 税率(主なもの) |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告額が本来より少なかった | 10% (追加税額が50万円等を超える部分は15%) |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった | 15% (税額50万円超は20%、300万円超は30%) |
| 不納付加算税 | 源泉所得税を納付しなかった | 10% (自主納付で5%に軽減) |
| 重加算税 | 意図的に所得を隠蔽・仮装した | 35% (無申告の場合は40%) |
| 延滞税 | 納期限に遅れて納付した | 年2.4%~8.7%(令和6年現在) |
調査結果に納得できない場合はどうする?
修正申告書の提出は「指摘に同意した」という意思表示になります。
もし指摘内容に納得できない場合は、安易に署名・押印してはいけません。その場合は修正申告をせず、税務署からの「更正」という処分を待ち、その処分に対して「不服申立て」(再調査の請求や審査請求)という手続きで争うことになります。
ただし、この手続きは専門的な知識を要するため、税理士への相談が不可欠です。
一人親方が税理士に相談・依頼するベストなタイミング
税理士に依頼する3つのメリット
- 精神的な安心感: 専門家が味方になることで、不安が大幅に軽減されます。
- 調査官との対等な交渉: 調査官の指摘に対して、法的根拠に基づき対等に交渉・反論してもらえます。不当な指摘を回避し、追徴税額を適正な範囲に抑える効果が期待できます。
- 修正申告等の手続きを代行: 複雑な手続きを全て任せることができ、本業に集中できます。
こんな時は税理士に相談しよう
- 税務署から調査の連絡が来た時: 日程調整の前に、まず相談するのが最善です。
- 帳簿の付け方に自信がない、書類が不十分な時: 事前準備の段階で相談すれば、調査当日までにできる対策を一緒に考えてもらえます。
- 調査官の指摘に納得がいかない時: その場で同意せず、税理士に交渉を依頼しましょう。
税務調査に強い税理士の選び方
- 一人親方や個人事業主の対応実績が豊富か: 自分の業種(建設業、運送業など)に詳しい税理士が望ましいです。
- 税務調査の立会い経験が豊富か: ホームページなどで年間の立会い件数や過去の事例を確認しましょう。
- 料金体系が明確か: 税務調査の立会い費用は、1日あたり5万円~15万円程度が相場です。どこまでの業務が含まれるのか(事前相談、修正申告書作成など)、契約前にしっかり確認しましょう。
【まとめ】正しい知識と準備が、あなたを守る最大の武器です
税務調査は、決して恐ろしいものではありません。
正しい知識を身につけ、日頃から誠実な記帳と資料保存を心がけていれば、過度に心配する必要はないのです。
今日から始める3つのアクション
- 帳簿と書類の整理: 本記事のチェックリストを活用し、現状を把握しましょう。
- 信頼できる税理士を探しておく: いざという時に慌てないよう、事前に相談できる専門家を見つけておくと安心です。
- 継続的な情報収集: 税に関する情報は常にアップデートしましょう。
この記事が、一人親方として真摯に事業に取り組むあなたの不安を解消し、事業運営の一助となれば幸いです
【免責事項】
本コンテンツは、公表されている情報や監修者の経験に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
個別の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
本コンテンツを利用したことにより生じたいかなる損害についても、当方では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。