会社設立にかかる費用はいくら?株式会社と合同会社の違いと節約ポイントを解説
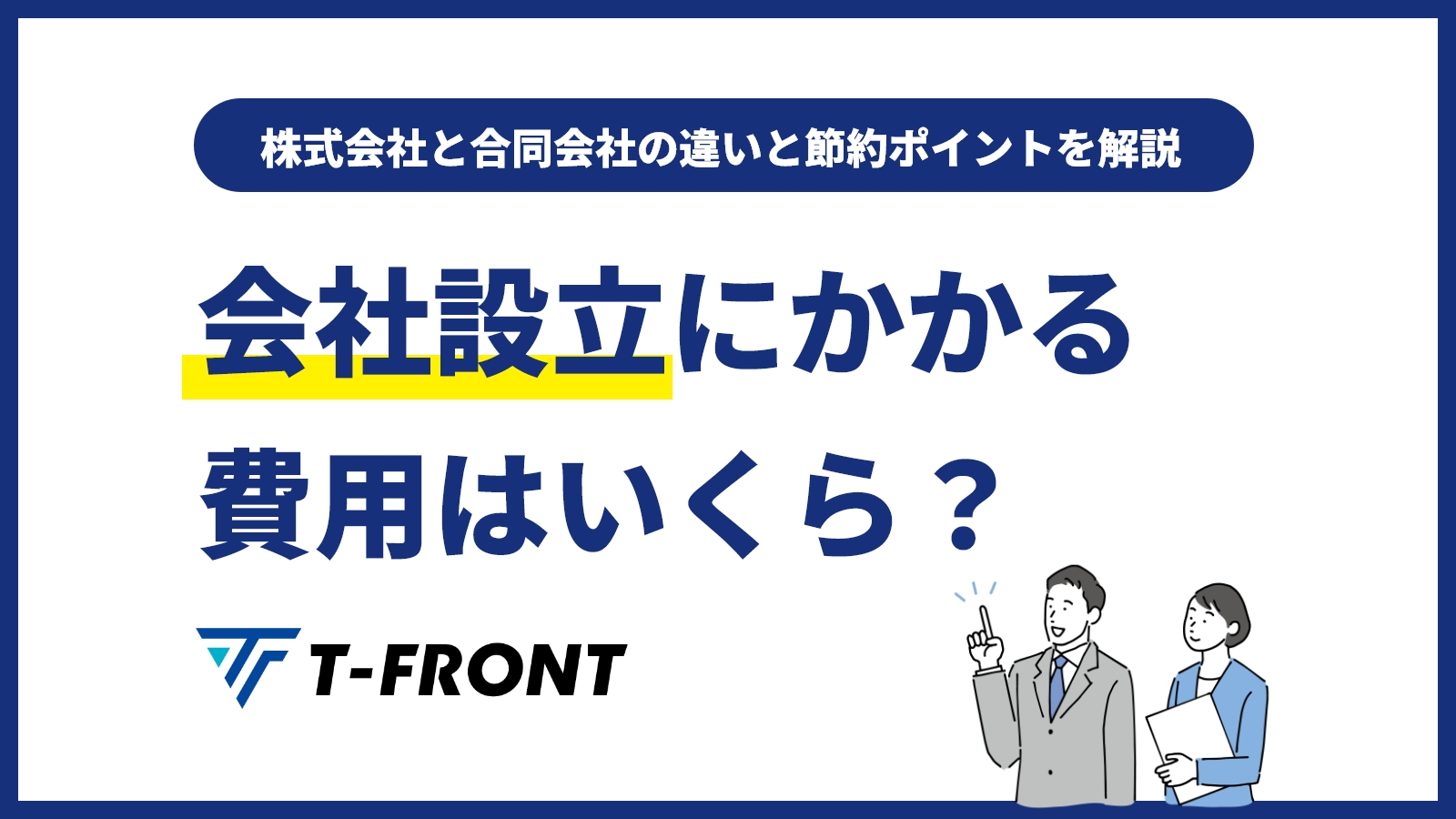
会社を設立したいけれど、
「何から始めればいいのか分からない」
「費用はどれくらい必要なのか不安だ」
――そう感じている方は決して少なくありません。
特に初めての起業では、会社設立の手続きや税務のことまで一人で判断するのは困難ですし、労力的にも大変です。
この記事では、会社設立にかかる費用や必要な準備、節約のコツについて、丁寧にわかりやすく解説しています。
一人で会社を作るには?会社設立に必要な準備と具体的な進め方を丁寧に解説
一人で会社を立ち上げたいけれど、「何から始めればいいのかわからない」という方は多いものです。
まずは会社設立に必要な手続きや費用、準備すべきものについて、要点を整理してご紹介します。
一人で会社を作るために押さえておくべき5つのポイント
- 会社形態を決める(株式会社・合同会社が主流)
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける(株式会社のみ)
- 資本金を用意し、自分の口座に払い込む
- 登記申請書類を作成し、法務局に提出する
- 印鑑や口座、各種届出など設立後の準備を行う
「一人で会社を作る」と聞くと、手続きが複雑そうで不安に感じる方も多いかもしれません。
しかし、2006年に施行された新会社法により、個人1人でも株式会社や合同会社を設立できる制度が整えられています。
従来は取締役が3人以上必要でしたが、今では取締役1名での設立が可能となりました。
会社設立の流れとしては、まず最初に株式会社にするのか、合同会社にするのかといった「会社形態」を選ぶところから始まります。
次に「会社の事業目的」「商号(会社名)」「本店所在地」「資本金の額」などを盛り込んだ定款を作成します。
なお、株式会社の場合はこの定款に対して公証人の認証を受ける必要があります。その後、定款で定めた資本金を自分名義の銀行口座に払い込み、設立に必要な書類と共に次の書類を法務局に提出します。
設立後に必要な手続き(一人起業でも必須です)
- 税務署への開業届提出、青色申告承認申請など
- 年金事務所への健康保険・厚生年金加入手続き
- 労働基準監督署・ハローワークへの届け出(従業員を雇う場合)
- 会社印の作成と印鑑登録
- 会社名義の銀行口座開設
このように、会社設立には設立時の準備だけでなく、設立後の手続きも含めた全体像を把握することが大切です。
また、これからご紹介する費用やスケジュール感も事前に理解しておけば、焦らず確実に進めることができます。
会社設立にかかる初期費用はどれくらい?株式会社・合同会社の費用を比較一覧で解説
会社を設立する際には、登記費用や定款作成費用など、想像以上に細かな出費が重なります。
まずは代表的な費用項目を整理した一覧表を下記にまとめました。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款用収入印紙代(紙定款の場合) | 40,000円 | 40,000円 |
| 定款認証費用(公証人手数料) | 約50,000円 | 不要 |
| 登録免許税 | 150,000円 または 資本金の0.7% | 60,000円 または 資本金の0.7% |
| 謄本手数料 | 約2,000円 | 不要 |
| 専門家への依頼費用(任意) | 50,000〜200,000円 | 50,000〜200,000円 |
| 設立にかかる合計費用目安 | 約222,000円〜 | 約100,000円〜 |
会社設立時には、どの会社形態であっても少なくとも10万円以上の初期費用がかかります。
特に株式会社を選んだ場合は、定款の認証費用や登録免許税が高くなるため、最低でも約22万〜25万円が一般的な相場です。
一方で合同会社は、定款認証が不要で手続きも簡素なため、約10万〜12万円程度で設立が可能です。
ただし、司法書士や行政書士に依頼する場合は、別途5万〜20万円ほどの報酬がかかるため、
総額で見ると株式会社なら約27万〜45万円前後、合同会社でも15万〜30万円前後になることもあります。
この章では、会社形態ごとの初期費用を詳しく整理しながら、電子定款の活用や自力での申請によって費用を抑える具体的な方法についても解説していきます。
定款に貼る収入印紙代はなぜ必要?電子化で節約できるポイントとは
この費用が発生する理由と節約のコツ
- 定款を紙で作成した場合は4万円の印紙税がかかる(法令による課税)
- 電子定款にすれば印紙税が不要になる(印紙税法非課税)
- 自分で電子定款を作成するか、代行業者に依頼する方法もある
株式会社と合同会社を問わず、会社設立時には必ず定款の作成が必要です。
この定款を紙で提出する場合には、印紙税として4万円を支払わなければなりません。
これは印紙税法の規定に基づいたルールがあるからであり、紙定款での提出を選んだ場合、この費用は避けることができません。
一方で、電子定款を利用すれば、この印紙税は非課税となるため、実質的に4万円のコストが不要になります。
電子文書は印紙税法上の「課税文書」に該当しないという解釈に基づいており、正式に認められた節税手段です。
会社設立費用節約のコツ
この電子定款の作成は専門家に依頼することができますが、自分で作って節約したいなら、次のような方法があります。
- 電子定款を自分で作成する(Adobe Acrobatや法務省ツールを活用)
- クラウド型の設立支援サービスを使う(freeeなど)
- 印紙代も込みのパック料金で提供する専門家に依頼する
上記の方法を活用すれば、確実に印紙税4万円を節約できます。
近年は、初心者でも扱いやすい電子定款作成サービスが増えており、法的にも安全で手軽に電子化が可能です。
また、電子定款はPDF形式でデータ保存できるため、再発行や再利用にも便利で、 紙の保管に比べて場所を取らず、検索や共有もしやすいため、会社設立の際はなるべく電子定款を選ぶようにしましょう。
株式会社だけ必要?定款認証費用の正体とカットする方法
この費用が発生する理由と節約のコツ
- 株式会社では定款に公証人の認証を受ける義務がある
- 合同会社は認証が不要なため、この費用は発生しない
- 事前予約・電子認証・最寄りの公証役場選定で効率化
定款認証費用とは、株式会社設立時に限って必要な「公証人による定款内容の確認と証明」にかかる費用です。
この手続きは、設立後のトラブル防止や、社会的信用の確保のために義務づけられており、一般的に、公証人の認証には5万円前後の費用がかかります。
一方で、合同会社はこの手続きが不要です。
そのため、同じ「会社」でも合同会社を選ぶことで約5万円のコスト削減が実現します。
節約のポイントは、株式会社の定款認証にかかる費用と手間を抑えるための工夫にあり、具体的には、次の3点が挙げられます。
会社設立費用節約のコツ
- 電子定款を利用することで、紙の定款よりも印紙代や手数料の一部を削減できる
- 居住地や事務所に近い公証役場を利用することで、交通費や移動時間を抑えられる
- 「設立パック」などのサービスを使えば、定款認証・登記・印鑑作成などをまとめて依頼でき、個別に手配するよりコスト管理がしやすくなる
これらはいずれも、株式会社を選ぶことで発生する「定款認証費用」とその周辺コストを効率的に抑えるための手段です。
なお、株式会社は合同会社と比べて社会的信用力が高く、将来的に資金調達や上場を視野に入れる方に好まれる会社形態です。
その分、設立時の手続きや費用はやや多くなりますが、長期的な事業成長を見据えて、適切に準備を進めるようにしましょう。
登録免許税は避けられない?設立形態と資本金で変わる金額の目安
この費用が発生する理由と節約のコツ
- 会社を登記する際に国へ支払う義務のある税金(法定費用)
- 株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円が必要
- 資本金を1,000万円未満に設定すれば増税を避けられる
登録免許税とは、会社を法務局に登記する際に必ず支払う必要のある国税です。
この税金は、会社を設立するすべての法人に共通して発生する法定費用として位置づけられています。
株式会社を設立する場合は、登録免許税の最低額が15万円と法律で定められています。
一方、合同会社では最低額が6万円とされており、会社形態によって負担額が大きく異なります。
ただし、資本金の金額が大きい場合には、税額が「資本金の0.7%」で計算され、この計算結果が最低額を上回る場合は、より高い方の金額が適用されます。
資本金が3,000万円の会社を設立する場合、0.7%に相当する21万円が登録免許税となり、株式会社では15万円ではなく21万円を支払う必要があります。
以下に、会社形態別で登録免許税の支払額がどう変わるのかをまとめました。
| 資本金の額 | 株式会社(登録免許税) | 合同会社(登録免許税) |
|---|---|---|
| 100万円 | 150,000円(最低額) | 60,000円(最低額) |
| 500万円 | 150,000円(最低額) | 60,000円(最低額) |
| 3,000万円 | 210,000円(0.7%適用) | 210,000円(0.7%適用) |
この登録免許税の負担を少しでも軽減するための工夫として、次のような節約のポイントがあります。
会社設立費用節約のコツ
- 資本金を999万円以下に設定することで、消費税の免税事業者としてのメリットが得られる可能性がある
- 合同会社を選べば、最低税額が低いため、初期費用を大きく抑えられる
- 自治体や国の創業支援制度、補助金・助成金を利用することで、実質的な資金負担を軽減することが可能
この登録免許税は、設立費用の中でも金額が高く、原則として避けることができない固定コストです。
しかし、会社形態の選択や資本金の設計を工夫することで、全体の負担を大きく変えることができる項目でもあります。
無理のない範囲で最適なバランスを取り、会社設立コスト全体の最適化を目指しましょう。
謄本手数料は意外な盲点?電子申請と紙申請で変わる手数料の実情
この費用が発生する理由と節約のコツ
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の発行に必要な費用
- 株式会社は登記後に取得が必要、合同会社では省略可能なケースも
- 電子交付を活用すれば費用と時間をカット可能
謄本手数料とは、会社設立後に取得する「登記簿謄本(正式名称:履歴事項全部証明書)」の発行にかかる費用のことです。
この書類は、法人の存在や代表者、所在地、資本金などの情報を第三者に証明するものであり、会社運営において何かと提出を求められる場面が多くあります。
特に株式会社では、取引先との契約締結や法人名義の銀行口座開設、助成金・補助金の申請などで提出が必須となるため、1〜2部の取得が一般的です。
1通あたりの取得手数料は約600円ですが、紙で申請する場合は手数料に加え、郵送日数や窓口対応の手間も発生します。
合同会社でも、登記簿謄本の提出が必要となるケースはありますが、個人事業に近い形で小規模に運営する合同会社では、提出が求められないこともあります。
さて、この登記簿謄本の取得費用も、少額ながら節約の工夫ができるポイントがあり、具体的には以下の3点の方法があります。
会社設立費用節約のコツ
- 必要最低限の部数のみを取得する
- 電子交付で取得すれば1通480円と紙より割安になる
- PDF形式で保存しておくことで、再発行の手間とコストを削減できる
実は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用すれば、電子交付で登記簿謄本を取得することが可能です。
登記簿謄本をPDFデータとして保存・共有できるため、取引先や関係先に提出する際も迅速に対応できます。
この機会に、法務局の電子申請システムやクラウドストレージを活用して、コストと時間の両面から業務効率化を図りましょう。
専門家への依頼費用は必要?自力との比較と依頼の判断基準
この費用が発生する理由と節約のコツ
- 司法書士や行政書士に登記手続きなどを依頼する際の報酬
- 依頼すればミスを防ぎつつ、書類作成や電子定款にも対応してもらえる
- 無料サービス・パックプラン・一部のみ依頼で費用を抑える工夫が可能
専門家(司法書士・行政書士など)への依頼費用は、会社設立手続きをスムーズかつ確実に進めるためのサポート費用です。
会社設立時には、定款の作成や電子認証、登記書類の準備、法務局への提出など、多くの専門的かつ煩雑な作業が発生します。
これらを専門家に一括で代行してもらえることで、会社設立時の「ミスの回避」「手続きの時短」「精神的な安心感」など、起業準備全体の負担を大きく軽減できます。
ただし、会社設立手続きを専門家に依頼する費用相場は依頼内容によって幅があり、一般的には5万円〜20万円程度が目安とされています。
株式会社・合同会社いずれの設立でも、これらの法的手続きのサポートを専門家に依頼することが可能です。
特に、電子定款の作成や提出方法に不安がある方にとっては、専門家への依頼が大きな安心材料になるでしょう。
さて、会社設立の中でも、それなりにコストがかかる専門家への依頼費用ですが、費用を節約できる方法は、いくつかあります。
会社設立費用節約のコツ
- 設立一式がセットになった「定型パック」を選ぶことで割安に
- 必要な部分だけを依頼し、書類作成など簡易な作業は自分で行う
- freeeやGMOなどの無料設立ツールを活用し、不明点のみサポートを受ける
法務や登記の知識がまったくない方は、多少高かったとしても「丸ごと依頼できるパック型サービス」がおすすめです。
会社設立の自分の作業負担を、ほぼゼロで進められるため、事業計画や営業準備など、本来注力すべき部分に集中できます。
もちろん、すべての手続きを丸投げすると費用は高くなるので、ご注意を。
また近年では「必要な部分だけを安価に依頼できるパッケージサービス」も増えており、予算に応じてプランを選ぶことで会社設立にかかる費用を抑えることができます。
資本金はいくらが正解?会社設立前に知っておきたい5つの基本ポイント
「資本金はいくらで設定すべきか?」という疑問は、起業を検討する多くの方が抱える共通の悩みです。
以下では、資本金の意味や注意点を整理した5つの重要ポイントをまとめました。
資本金設定のポイント一覧
- 資本金は1円からでも会社設立は可能(法改正により最低資本金制度が廃止)
- 実務では50万円〜300万円程度が一般的な設定相場
- 資本金額は対外的な信用力に大きく影響する
- 資本金1,000万円以上だと設立初年度から消費税課税事業者になる
- 資本金は設立後の運転資金や事業資産に使ってよいが、使途には計画性が必要
資本金とは、会社が事業をスタートする際に用意する「初期の運転資金」かつ「会社の信用を示す目安」です。
法的には1円からでも設立は可能ですが、実際にはあまりにも少額だと信用力を疑われる可能性があります。
取引先が会社概要を見たときに「資本金が10万円」とあれば、継続的な取引に不安を感じるかもしれません。
また、銀行口座開設や融資審査、助成金の申請においても、資本金の金額は一定の評価項目になります。
そのため資本金は一般的には、50万〜300万円の範囲で資本金を設定する起業家が多いようです。
この範囲であれば、運転資金としての実用性もあり、対外的な信用にも一定の説得力を持たせられます。
一方、資本金を1,000万円以上に設定すると、消費税が初年度から課税されるという税務上の注意点もあります。
設立時には免税事業者としてスタートできるよう、資本金を999万円以下に抑える判断も多く見られます。
資本金は、設立後に設備購入・人件費・広告費などに自由に使えますが、「使い切ってしまえば残高ゼロ」になります。
そのため、単に金額を設定するだけでなく、どう使い、どのように資金繰りを計画するかという視点も重要です。
会社設立にかかる費用まとめ|ポイントと専門家活用のススメ
起業を考える方にとって、会社設立に必要な費用や手続きは想像以上に煩雑です。
この記事では、主に次のようなことをご紹介させて頂きました。
この記事で押さえておきたい5つのポイント
- 設立形態(株式会社/合同会社)によって費用や手続きが大きく異なる
- 定款は電子化することで印紙代4万円を節約できる
- 登録免許税や定款認証費用など、避けられない法定コストがある。
- 資本金は1円からでもOKだが、信用や税務上の配慮が必要
- 専門家に依頼すればミスを防ぎつつ、時間と手間も大幅に削減できる
会社設立は一見シンプルに見えて、実際には税務・法務・手続きの知識が求められる分野です。
特に、定款の作成や税務署への届け出、社会保険手続きなどは正確性が求められるため、専門家のサポートを得ることでトラブルや手戻りを未然に防ぐことができます。
また、会社設立後の税務対応や節税策のアドバイスも受けられるため、起業後の経営の安定にもつながります。









