【完全ガイド】会社設立の流れ|初心者でも失敗しない7ステップと設立日・登記・保険加入まで徹底解説
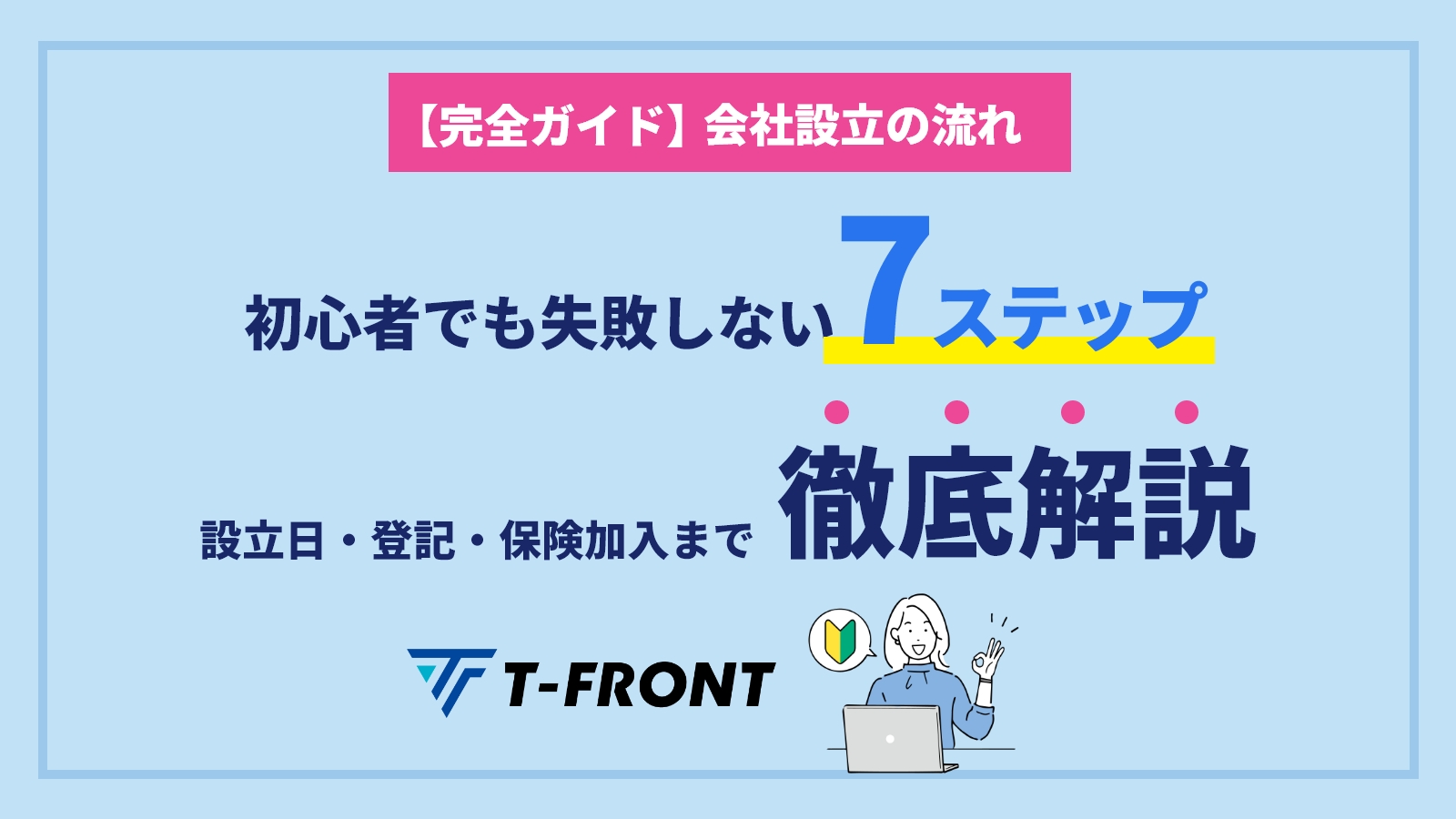
会社を設立したいけれど、「何から始めればいいのか分からない」「手続きが煩雑そうで不安だ」と感じていませんか?
初めての会社設立は、多くの書類作成や役所への申請が必要となり、思った以上に手間と時間がかかるものです。
専門的な知識が求められる場面も多く、ひとりで進めるには不安がつきまとうかもしれませんね。
そんな経営者や個人事業主の方のために、この記事では会社設立の流れと注意点について、わかりやすく丁寧に解説しています。
初心者でも安心!会社設立の流れを一つずつ丁寧に解説
会社設立は、やるべき手続きが多く、一見すると複雑に見えるかもしれません。
しかし、各ステップを順番に理解して進めれば、自分ひとりでもしっかりと対応可能です。
次にの表で、会社設立の基本的な流れを初心者向けに整理しました。
会社名、所在地、目的、資本金、役員構成などを明確にする
会社のルールを文書化。紙または電子定款を作成
公証役場で定款に公的な証明を受ける(株式会社の場合)
発起人の口座に資本金を振り込むことで資金を確保
法務局に必要書類を提出して登記申請
登記完了後、会社が法的に成立。証明書や印鑑カードの取得
税務署や年金事務所への届出、銀行口座開設などを実施
会社を立ち上げるには、段階ごとに決めるべきこと、作成する書類、提出先が明確にあります。
「思っていたより簡単そう」と感じる方もいれば、「これは一人では不安」と思う方もいらっしゃるでしょう。
特に定款作成や登記書類の準備は、専門用語や法律的な表現が多く、慣れていない方にはハードルが高い部分です。
また、資本金の払い込みや法務局への申請は、手順を誤るとやり直しが発生するリスクもあります。
そのため、全体像をしっかりと把握した上で、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが、失敗を避ける鍵となるでしょう。
この章では、会社設立の基本的な流れとやるべきことを詳しく解説します。
最初の一歩をしっかりと!会社の基本事項を決定する
会社を設立する際、最初に行うべきことは「基本事項の決定」です。
この段階では、会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金の額、設立日、役員の構成などを明確にします。
これらの情報は、定款の作成や登記の申請など、後のすべての手続きの土台になります。
- 【目的】会社の全体像と方向性を明確にするための土台を作る
- 【やるべきこと】会社名・所在地・目的・資本金・役員を具体的に決める
- 【注意点】重複する会社名や不適切な事業目的の記載に要注意
これらは、後の定款作成や登記手続きで必要不可欠な情報なので、最初の段階でしっかり考えて決めましょう。
中でも事業目的は、実際に行う業務と一致した具体的な内容を記載する必要があります。
なぜなら、融資申請や補助金の審査、許認可取得の場面で、この記載内容が判断材料となため、事業目的があいまいな表現だった場合は、支援対象から外れる恐れがあります。
会社名(商号)についても実は注意が必要です。
商号は簡単に変更できる?
会社名(商号)は設立後でも変更可能ですが、以下のような手続きとコストが発生します。
- 登記変更申請(登録免許税:3万円〜)
- 新しい定款の作成または変更
- 法人銀行口座・印鑑証明書・契約書等の一括変更
- 名刺・Webサイト・広告媒体などの刷新
このように、商号の変更は思った以上に負担が大きいため、設立時に慎重に選定しておくことが肝心です。
将来的な事業展開・商標登録・ドメイン取得の可否なども含めて、多角的な視点で検討しましょう。
また、役員構成や任期も「将来変更するかもしれないから」と安易に決めてしまうと、後から登記変更や株主総会が必要になり、手間やコストがかさむので、長期的な視点で組織設計を行うことが、結果的に負担を軽減します。
このように、基本事項の決定は単なる「最初の作業」ではなく、今後の運営効率や手続きのしやすさに直結する「経営設計の要」と言えるのです。
会社のルールを形にする「定款の作成」
定款(ていかん)は、会社の憲法とも言える文書です。
会社名、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成、決算期、公告方法などを記載し、会社運営の枠組みを明文化します。
- 【目的】会社の基本ルールを法的に明文化するため
- 【やるべきこと】定款に商号・目的・機関設計・公告方法などを記載する
- 【注意点】曖昧な文言や法令違反の内容を記載しないこと
また定款には、記載しなければ登記が受理されない「絶対的記載事項」と、会社の任意の取り決めを記す「任意的記載事項」の2種類があります。
以下の表でその違いを整理しました。
| 分類 | 内容 | 主な記載事項 |
|---|---|---|
| 絶対的記載事項 | 登記に必須。欠けていると会社設立は認められない | ・会社の目的 ・商号(会社名) ・本店所在地 ・設立に際して出資する財産の内容とその価額または最低額 ・発起人の氏名または名称及び住所 |
| 任意的記載事項 | 会社独自のルールを追加できる。記載しなくても設立は可能 | ・取締役の員数や任期 ・株式の譲渡制限 ・事業年度 ・公告方法 ・利益配当の基準など |
初めて定款を自作する方は、定型テンプレートを活用することが多いですが、自社の実態に合っているかどうかの内容チェックは必ず行ってください。
例えば、事業目的が曖昧すぎると、許認可の取得や融資申請の際に審査で不利になる可能性があります。
また、後から定款の記載内容(例:役員の任期や公告方法など)を変更する場合には、株主総会の特別決議が必要です。
この手続きには時間とコストがかかるため、できるだけ将来の展開も見据えて柔軟に設計しておくと安心です。
不安な場合は、司法書士や税理士など会社設立に詳しい専門家に一度相談することで、最初から無理や無駄のない形に整えることができます。
定款の内容に不備があると、登記自体が却下されることもあるため、最初の一歩ほど慎重に進めましょう。
法的に効力を持たせるための「定款認証」
株式会社を設立する場合、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。
これは、法的効力を持たせるための公的な確認手続きであり、合同会社にはこの認証は不要です。
- 【目的】定款を正式な文書として公証役場に認めてもらうため
- 【やるべきこと】定款と必要書類を持参し、公証人の認証を受ける(株式会社のみ)
- 【注意点】電子定款でない場合は印紙代4万円が必要になる
定款認証を受けるためには、公証人との面談や事前予約、本人確認書類の提示といった、いくつかの準備が求められます。
特に忙しい設立直前の時期には、抜け漏れがないよう注意が必要なので、次の表で具体的にどんな業務があるのかを理解しておきましょう。
定款認証の際に必要な業務一覧
定款認証には次のように事前準備が必要です。
公証役場に電話等で日程を予約。提出内容の確認も事前に相談可
定款(紙またはPDF)、発起人の印鑑証明書、本人確認書類など
公証人の面前で定款内容の確認、認証手数料の支払いと署名
まずは公証役場への予約から始まり、必要な書類一式を整えてから公証役場へ訪問します。
定款の内容は公証人が一字一句確認するため、事前に自社の情報に誤りがないかを事前にしっかりとチェックしておくようにしましょう。
また、公証人とのやりとりでは、発起人の身分確認や署名が求められます。
なお、紙定款で認証を受ける場合は、収入印紙代として4万円の費用が発生します。
一方、電子定款を用いれば、PDF形式での提出により印紙税が課されないため、この費用を節約できます。
これは国税庁の規定によるもので、「紙に出力して提出しない=課税文書に該当しない」という扱いになるからです。
このような理由から、近年では電子認証に対応したクラウドサービスや専門家(司法書士・行政書士)に依頼するケースが増えています。
電子定款を利用することで、紙定款の準備や提出の手間を軽減でき、なおかつコスト面でもメリットが大きいため、特に初めての方は電子定款を選ぶようにしましょう。
一見すると、この手続きは形式的なものに見えるかもしれませんが、この定款認証のステップは、後の登記審査に直結する正確さが求められる重要工程です。
早めの準備と、専門家の助言を受けることで、スムーズに乗り越えることができるでしょう。
設立資金の用意と証明|資本金の払い込み
資本金の払い込みは、会社が事業を開始するにあたっての「信用」と「資金の裏付け」を示す重要な手続きです。
- 【目的】会社の活動資金を明確にし、法的な要件を満たすため
- 【やるべきこと】発起人名義の口座に資本金を入金し、その証明を取得する
- 【注意点】定款認証日以後に払い込む必要がある。日付や金額の誤りに注意
株式会社を設立する際、定款認証が終わったら、次に必要なのが資本金の払い込みです。
これは会社のスタート資金となるものであり、登記の際に「確かに出資がなされたこと」を証明しなければなりません。
代表発起人名義の個人口座に、他の出資者を含めた全員の出資金額をまとめて入金します。
その後、通帳の表紙・口座情報のページ・入金記録のあるページをコピーし、「払込証明書」という書類とともに法務局に提出します。
このステップは、会社法により出資の履行が義務付けられているため、法務局で登記申請を受理してもらうための前提条件となります。
もし証明できなければ、登記が却下され、会社の設立そのものが成立しません。
そのための次のことに注意してください。
資本金払い込み時の注意点一覧
| 注意点 | 理由・補足説明 |
|---|---|
| 定款認証日“以降”に払い込むこと | 認証前の入金は会社法の要件を満たさず無効扱いとなる。やり直しが必要になるため注意 |
| 通帳の記載内容を正確に整える | 発起人名義の口座を使用し、入金日・金額・名義が定款の内容と一致している必要がある |
| 出資の方法に関わらず記録を明確に | 一括でも個別でもよいが、振込人名・金額・日付が明確でなければ証明として認められない |
資本金払い込みは、登記審査でも厳しく確認される項目であり、そのため記録の整合性やタイミングに注意し、法的要件を正確に満たす必要があります。
このように、資本金の払い込みは単なる“入金”ではなく、「会社設立の信頼性」を担保する法的証拠です。
初めての方や時間が限られている方は、司法書士や税理士に払込証明書の作成代行や確認を依頼することで、ミスのない対応が可能になります。
会社設立を確実に行いたい方は、この段階で専門家のサポートを活用することをおすすめいたします。
書類ミスが命取り?登記書類の作成と提出
会社設立の核心となるのが、登記書類の提出です。
法務局へ申請を行うことで、会社は正式に「法人格」を取得するため、このステップでは多くの書類を正確に準備しなければなりません。
- 【目的】法務局で会社の設立を正式に登記するための準備
- 【やるべきこと】定款・就任承諾書・印鑑届出書など必要書類を揃える
- 【注意点】記載ミスや添付漏れがあると登記が却下されることもある
これらの書類には一つひとつ厳密な書式や記載ルールが定められており、形式や内容に不備があると、法務局での受理が却下されることも少なくありません。
そのため、高度な正確性と細心の注意が求められる重要な工程です。
登記申請書類の細かな決まりと注意点
下記の表のとおり、登記申請書類の作成や形式にはそれぞれ独自のルールと注意点があります。
| 書類名 | 主な記載・形式ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 定款 | 絶対的記載事項を含める。会社名、目的、所在地など | 記載内容が不明確だと公証人の認証が受けられない |
| 設立登記申請書 | 定型フォーマットに沿って、会社情報・設立日等を記載 | 記載ミスや提出書類の添付漏れで登記が却下される |
| 就任承諾書 | 役員本人の署名が必須 | 署名がない場合、就任の意思確認が取れず却下対象に |
| 払込証明書 | 資本金の額、払い込み日、通帳写しを添付 | 入金日・金額の記録と定款の整合性に注意 |
| 印鑑届出書 | 会社代表印を届け出る書類 | 提出がないと印鑑カードが発行されず取引に支障 |
| 印鑑証明書(取締役) | 発行日から3か月以内のものを使用 | 有効期限を過ぎると無効。事前取得のタイミングに注意 |
例えば、就任承諾書では本人の署名が必要不可欠であり、印鑑証明書には発行日から3か月以内という有効期限が定められています。
これらを見落とすと、書類が不備扱いとなり、登記のやり直しを余儀なくされます。
書類作成に少しでも不安がある方は、司法書士や税理士のサポートを受けることで、こうした細かな要件をすべて網羅的にカバーすることができます。
また、一度登記が却下されると、再申請のために新たな書類の作成・提出準備が必要になり、法務局での処理期間を含めて1〜2週間程度の遅れが発生することもあります。
この遅れにより、銀行口座の開設や契約締結、各種届出など事業開始のスケジュール全体が後ろ倒しになる可能性があるため、慎重な準備が求められます。
法的に会社が生まれる瞬間|登記完了と会社設立
登記申請が無事完了すると、会社は法的に成立し、法人格を取得した「株式会社」として公的に認められる状態になります。
この日が「設立日」となり、登記事項証明書などの公的書類の取得が可能になります。
- 【目的】法人格を取得し、対外的にも正式な「会社」として認められるため
- 【やるべきこと】登記完了後、登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書を取得する
- 【注意点】設立日は登記申請日になる。遅れると希望日での設立ができなくなる
このときに交付を受けるのが「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」です。
これは会社の名称・所在地・役員構成・資本金など、法務局に登記されたすべての情報を記載した正式な証明書です。
この書類は取引先との契約時や、法人名義の銀行口座開設時、助成金申請などの行政手続きでも頻繁に提出を求められる非常に重要な書類です。
さらに、登記完了後には「印鑑カード」も取得できます。
このカードを使うことで、法人の実印に対する「印鑑証明書」を発行できるようになり、正式な契約締結や登記変更手続きの際に不可欠な証明手段となります。
この時点でようやく、法人名義での資金管理・契約締結・社会保険の加入・税務署への届出など、会社としての実務を本格的に開始できる状態になります。
会社の設立日と登記申請日の注意点
会社設立の手続きを進める中で、意外と見落としがちなのが「設立日」の扱いです。
この日付は、単なる書類上の日付ではなく、今後の税務処理や助成金申請、決算期の管理などにも大きく関わってきます。
ただし、注意が必要なのは、「会社の設立日」=「登記申請日」であるという点です。
会社は、法務局に登記申請を行った日をもって法的に成立したとみなされます。つまり、どんなに準備が整っていても、登記申請をしなければ会社は存在しない扱いになるのです。
資本金の払い込みや書類の準備に時間がかかり、申請日が想定より遅れてしまうと、希望した設立月に間に合わず、決算月の調整が難しくなる、あるいは年度内の補助金申請の対象から外れてしまうといった影響が出る可能性があります。
たとえば、補助金の要件として「3月末までに設立済みであること」が定められている場合、登記申請日が4月1日になるだけでその年の申請資格を失うこともあります。
そのため、設立日を意識した逆算スケジュールの設計が重要です。
特に年度末や月末に会社設立を予定している場合は、数日の遅れが致命的な結果を招くこともあるため、資本金の払い込みや書類作成は余裕をもって早めに着手するようにしましょう。
設立後こそ大切!各種届出と実務手続き
会社が登記によって設立されたからといって、すぐにすべての準備が整うわけではありません。
設立後も、さまざまな行政手続きや実務対応が待っています。これらを適切に行うことで、ようやく“動ける会社”としての体制が整います。
- 【目的】会社としての活動を法的・実務的に整備し、円滑に事業を開始するため
- 【やるべきこと】税務署、社会保険事務所、金融機関への届出や開設手続きを行う
- 【注意点】期限のある届出が多く、提出忘れや遅れに注意が必要
会社設立後は、登記が完了したからといってすべての準備が終わるわけではありません。
むしろここからが本当のスタートです。
行政機関への各種届出や、事業運営に必要な環境整備を進めていく必要があります。
この際に特に重要なのが、「税務・労務関連の届出」と「法人名義の銀行口座開設」です。
これらの手続きを正しく行っておかないと、税務署からの指摘や社会保険の未加入トラブル、資金の受け取り口座がないといった事態が起こる可能性があります。
設立後に行う主な手続き一覧
設立後の手続きは「提出先がバラバラ」であり、次の表のように期限が異なることが特徴的です。
例えば、税務署への法人設立届出書は2か月以内ですが、労務関連は雇用日から数日以内とタイトなものもあります。
| 手続き名 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払い開始から1か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立日から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日まで |
| 法人設立届出書(地方税) | 都道府県税事務所・市区町村 | 自治体により異なる |
| 健康保険・厚生年金の新規適用届 | 年金事務所 | 従業員を雇用した日から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金の新規適用届 | 労働基準監督署・ハローワーク | 労働者を雇った翌日から10日以内 |
| 法人名義の銀行口座開設 | 各金融機関 | 登記完了後、随時 |
また法人名義の銀行口座を開設する際には、登記事項証明書・印鑑証明書・定款などの提出が求められ、銀行によっては面談や事業内容の確認を受けることもあります。
法人名義の銀行口座の開設までに数日〜2週間ほどかかるケースもあるため、資金の動きがある前に準備を進めるのが望ましいでしょう。
これらのことを忘れたり遅れたりすると、青色申告の適用が受けられない、助成金の申請に間に合わない、罰則が科されるといったリスクもあります。
そのため、設立後1〜2か月間は、実務対応の集中期間と捉えて、早め早めの行動が安心につながります。
もし時間や知識に不安がある場合は、税理士に設立後の顧問契約を依頼し、すべての提出を一括サポートしてもらうという選択肢も考えましょう。
会社設立後も気が抜けません!事業開始前にやるべき手続き一覧
登記が完了して法人格を取得したあとも、実際に事業をスタートするには各種の届出や準備が必要です。
以下の表では、設立後に必ず行うべき代表的な手続きを時系列に整理しました。
| 手続き項目 | 提出先 | 期限 | 目的・ポイント |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立日から2か月以内 | 法人の存在を税務署に届け出て、課税対象とする |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日 | 青色申告による税務上の優遇を受けるための申請 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払開始から1か月以内 | 従業員への給与支払いに関する届け出 |
| 法人設立届出書(地方税) | 都道府県・市区町村 | 自治体ごとに異なる | 地方税課税のための登録 |
| 健康保険・厚生年金の新規適用届 | 年金事務所 | 従業員の雇用から5日以内 | 社会保険への新規加入手続き |
| 労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届 | 労働基準監督署・ハローワーク | 雇用開始から10日以内 | 労災・雇用保険の適用を受けるための届出 |
| 法人名義の銀行口座開設 | 金融機関 | 登記完了後、随時 | 取引・入出金のための法人口座開設 |
会社設立後には、税務署や社会保険事務所、地方自治体、金融機関などへの届出や申請業務が一斉に発生します。
これらはすべて、会社が法的に正しく機能し、事業を継続的に行うために不可欠なステップです。
特に、税務関連の申請や社会保険の手続きには明確な提出期限が設けられており、遅延すると罰則や不利益が発生する可能性もあります。
また、法人名義の銀行口座は資金管理の起点となるため、事業開始前に余裕をもって準備しておくべきです。
提出する内容や書類の作成に対して不安がある場合は、税理士や社労士といった専門家にサポートを依頼することをおすすめします。
設立後すぐに!税務署への届出は「忘れた」では済まされません
会社を設立したら、すぐに対応すべきが「税務署への各種届出」です。
提出すべき主な税務書類とその提出期限、注意点を 以下の表で整理しました。
| 届出書類名 | 提出先 | 提出期限 | 主な目的・ポイント |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立日から2か月以内 | 会社が設立されたことを税務署に通知し、課税対象として登録される |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立日から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日 | 青色申告による税制上の優遇措置を受けるための申請 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払開始から1か月以内 | 従業員や役員に給与を支払う際に必要な届出 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 随時(希望する場合) | 給与の源泉徴収税を半年に一度まとめて納められる特例を申請する |
会社を設立すると、税務署への届出は避けて通れません。
最も基本的なのが「法人設立届出書」で、これは会社が法的に存在していることを税務署に報告し、納税義務を果たすための第一歩です。
加えて「青色申告の承認申請書」を提出しておくと、欠損金の繰越控除や特別償却などの優遇措置を受けられます。これは将来的な節税対策にもつながる重要な選択です。
ただし、提出期限を過ぎるとその年度の青色申告は適用されないため、注意しましょう。
役員報酬や従業員給与を支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」も必要で、仮にこの届出を出さずに支払いを始めてしまうと、源泉徴収や納税に関するトラブルにつながる可能性があります。
また従業員数が少ない法人であれば「源泉所得税の納期の特例申請」を行うことで、毎月の納税を年2回にまとめることも可能になり、経理処理の負担を軽減するメリットがあるので必ず提出を!
社会保険・労働保険の手続きは雇用の有無で分かれる!
会社設立後は、従業員を雇うかどうかによって、加入すべき保険が大きく異なります。
社会保険・労働保険の種類と加入要件は次の表のようになります。
| 保険の種類 | 加入義務の有無 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | 法人は従業員0人でも加入義務あり | 年金事務所 | 設立後速やかに | 代表取締役1人でも加入対象 |
| 厚生年金保険 | 健康保険と同時加入 | 年金事務所 | 設立後速やかに | 設立後速やかに 法人の役員も対象 |
| 労災保険 | 労働者を1人でも雇用する場合は必須 | 労働基準監督署 | 雇用の翌日から10日以内 | 役員のみの場合は不要 |
| 雇用保険 | 週20時間以上勤務の従業員を雇用する場合 | ハローワーク | 雇用の翌日から10日以内 | 65歳未満の従業員が対象 |
会社を設立すると、役員のみの場合でも健康保険と厚生年金保険には必ず加入しなければなりません。
これは法人である以上、たとえ従業員がいなくても「会社=保険適用事業所」とみなされるためです。
仮に代表取締役1名だけでも、社会保険の新規適用届と被保険者資格取得届を提出する必要があります。
一方で、労働保険(労災保険・雇用保険)は「従業員の雇用」が前提です。
アルバイトやパートを1名でも雇用した時点で労災保険の加入が義務付けられますし、雇用保険については、週20時間以上勤務・31日以上の雇用見込み・65歳未満などの条件を満たす場合に必要となります。
なおアルバイトやパートを一切雇用しない場合、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入義務は基本的に発生しません。
役員のみで運営されている法人は、労働者に該当しないため、労働保険の適用対象外となります。
ただし、後に人を雇う予定がある場合は、事前に加入条件を確認しておくと安心です。
また、こうした条件を正確に把握しておかないと、未加入状態での労働災害や行政指導、助成金の不支給といったリスクにつながります。
また、申請書の提出期限は非常に短く、雇用の「翌日から10日以内」に提出しなければならないものもあります。
初めての設立で不安な方や、従業員をすぐに雇用する予定のある方は、社会保険労務士への相談・代行依頼も検討すべきでしょう。
会社設立の流れと注意点|専門家と進める安心の第一歩
会社設立は、単に法人格を取得するだけでなく、設立後の手続きや法令順守までを一貫して整える必要があります。
次の記事内で紹介したことをしっかりと覚えておきましょう。
- 設立の準備段階での基本事項の決定は、事業の土台づくりに直結します
- 定款の作成・認証には法的な記載要件があり、不備があると設立が無効になる可能性があります
- 資本金の払い込みや登記書類作成には、日付・内容・証明方法に厳格なルールがあります
- 登記完了後も、税務署・年金事務所・労基署などへの届出が立て続けに必要となります
- 書類作成や申請期限の管理には高度な正確性が求められ、専門家の力が大きな助けになります
記事内でも触れましたが、定款の記載、資本金の払い込み、登記書類の作成、各種届出の期限管理……一つでも抜け漏れがあれば、設立が遅れたり、思わぬ不利益を被るリスクもあります。
だからこそ、初めて会社を設立する方や、正確かつスムーズな進行を重視したい方には、信頼できる税理士のサポートを受けることを強くおすすめします。
税理士に相談することで、複雑な作業の手間を省きつつ、節税・経理体制の構築・設立後の助成金対策まで幅広くカバーできます。
“最も頼れる税理士”を目指す「T-FRONT」では、設立前の無料相談から登記書類のサポート、開業後の経理支援までワンストップで対応。
経営者の不安に寄り添いながら、正確・迅速な手続きで、あなたの新しいスタートを徹底サポートいたします









