過去に税務調査を受けていると再調査の可能性はある?税務署の判断基準と対応策を解説
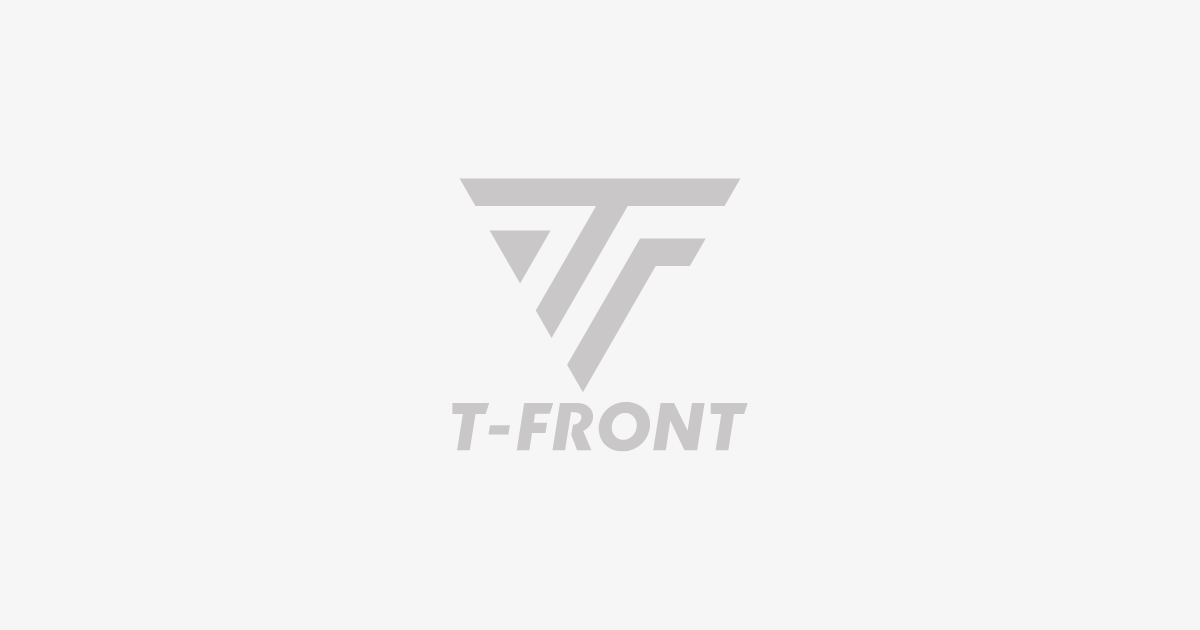
税務調査を一度受けたことがあると、「もう二度と来ないでほしい」と願うのが本音でしょう。しかし、実際には再び税務調査が行われることもあります。本記事では、「過去に税務調査を受けていると再調査の可能性はあるのか?」という疑問に対し、税務署の判断基準や再調査のリスク、対策までを詳しく解説します。
税務調査を経験した経営者や個人事業主の方、またはこれから調査が入る可能性がある方にとって、備えとなる情報をお届けします。
再調査の可能性はあるのか?
結論から言うと、過去に税務調査を受けていても再調査の可能性は十分にあります。
税務署は、調査を受けたという事実だけでは将来の調査対象から外すことはありません。むしろ、過去の調査で指摘事項があった場合や、不明確な取引、申告内容に継続的な疑念がある場合は、数年後に再度調査の対象となることがあります。
再調査の判断基準とは?
再調査が行われるかどうかは、税務署側の内部基準や情報収集結果に基づいて判断されます。主な要因は以下のとおりです:
- 過去の調査で修正申告が行われたか
- 調査後の申告状況に改善が見られるか
- 同業他社と比較して売上や利益率に乖離がないか
- 外部からの情報提供(タレコミや関連会社からの情報)
- 無申告や不自然な赤字決算の継続
税務署は「リスクベースアプローチ」という手法を採用しており、調査の効率性を重視しています。そのため、調査経験があっても「リスクが高い」と判断されれば再調査の対象になるのです。
よくある誤解
「一度税務調査を受けたからもう大丈夫」と考えてしまうのは大きな誤解です。税務署は通常、3年〜5年程度のサイクルで同じ納税者に調査を行うこともあります。また、法人とその代表者個人、関連会社が別々に調査対象になるケースもあるため、調査を受けた会社と別の関連先に税務署が来る可能性もあります。
さらに、過去の調査内容が「表面的なチェック」にとどまっていた場合、より詳細な調査が後日行われることもあり得ます。
実務での注意点
税務調査後も、以下の点に注意して申告・帳簿管理を徹底することが重要です:
- 調査で指摘された点を継続的に改善しているか
- 会計帳簿や領収書、契約書の整備状況
- 節税と脱税の境界を意識した取引の記録
- 資金の流れ(特に現金取引)を明確にすること
特に調査後に申告ミスや不備が続くと、「指摘されたにもかかわらず改善がない」と見なされ、悪質と判断される恐れがあります。
税理士としての支援内容
税務調査や再調査に備えるためには、税理士などの専門家のサポートが有効です。具体的には以下のような支援が可能です:
- 調査時の立ち会いや税務署との対応代行
- 調査後の改善指導とチェック体制の構築
- 節税スキームの法的リスク評価
- 書面添付制度を活用した信頼性の確保
特に書面添付制度は、税理士が内容を確認し署名を行うことで、税務署側が事前に税理士へ意見聴取する仕組みです。これにより、いきなりの調査を防ぐ効果も期待できます。
まとめ
過去に税務調査を受けていても、再調査の可能性は十分にあります。特に指摘事項があった場合や、その後の申告が不自然な場合は再度の調査対象になることも。調査を受けた経験があるからこそ、継続的な改善と帳簿管理の徹底が必要です。
「また税務署が来たらどうしよう」と不安を抱えている方は、一度税理士などの専門家に相談し、体制の見直しを図ることをおすすめします。









